金輝 発達障害アートカフェ・バー
発達障害ならどんな教師になれるかチェックする方法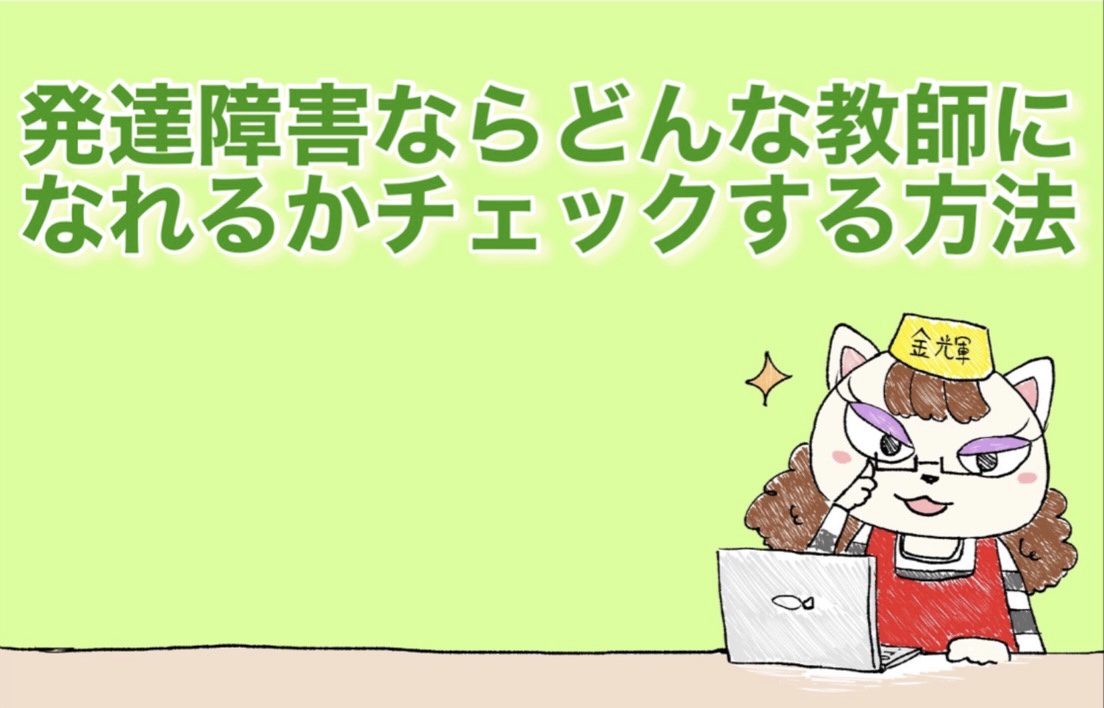
発達障害が教師になる前にチェックして欲しい箇所
──発達障害のある私が“教師”になるまでに気づいたこと。 「好きな教科を教えたい」 「学生時代にお世話になった、あの先生みたいになりたい」 「教えるって、楽しい。だから、教師になりたい」 そんなまっすぐな気持ちから「先生を目指したい」と思った方も多いのではないでしょうか? 実際、勉強が得意で“知識を分かち合う喜び”にワクワクできる人ほど、教師はぴったりの職業でもあります。 でも… 理想と現実には「あるギャップ」があるのも事実なんです。 ■ 金輝 発達障害カフェバーで聞いた“本音”:「変えてやると思って教師になったけど…」 ある日、金輝(発達障害カフェバー)に来たお客様のこんな話が心に残っています。 「学生時代、学校が大っ嫌いだったんです。だからこそ、自分が変えてやる!って思って教師を目指しました」 そう、「昔の自分のような子どもを救いたい」という思いから教師を志す人も多いんです。 しかし、今の学校現場は、昔とはちょっと様子が違うかもしれません。 ・生徒指導だけでなく保護者対応まで求められる ・教科の授業だけではなく、特別支援・ICTなどスキルの幅が広い ・教員間の人間関係が難しく、孤立してしまうことも 実際に、教師になれたものの職場いじめに遭い、うつ病で退職してしまった発達障害当事者の方もいます。 ■ それでも、「教えることが好き」な気持ちは、本物だった。 確かに、教員として全日制の学校に勤めるにはマルチタスク能力や協調性が問われがち。 でも、「教えることが好き」「知識を伝えるのが得意」な人には、違う形で教師になる道もあるんです。 たとえばこんな教育現場👇 ・フリースクールやオルタナティブ教育 ・発達障害支援に特化した個別指導塾 ・オンライン家庭教師やリモート講師 ・キャリア講師や出張授業などの単発講師 ・学校ではなく、教育系YouTuberやインフルエンサーとして情報発信者になる道 「先生になる=学校の先生」と思いがちですが、「教える」というスキルを活かせる場所は他にもたくさんあるんです。 ■ 向いてないのは、あなたじゃなくて「環境」かもしれない。 大事なのは、「向いてない」と自分を責めることではなく、 「自分に合った教育のフィールド」を見つけることです。 ・生徒が真面目じゃないから苦しい ・雑務が多すぎて疲れ果てた ・会議で話がかみ合わない… それ、全部あなたが悪いわけじゃありません。 発達障害という特性を理解してもらえない環境の問題も、大きいのです。 ■ 最後に──あなたの「教えたい」が、誰かを変える日がくる。 この記事では、「発達障害のある人が教師になれるのか?」という疑問に、現実と希望の両面からお伝えしました。 もし、今の学校教育の枠に自分が合わないと感じたなら、どうかそれで夢を諦めないでください。 「教える力」は、あなたの中にちゃんとある。 あとはその力をどこで、どう活かすかだけ。 教師という肩書きだけにとらわれず、「教える人生」そのものを楽しめる方法が、きっとあるはずです。 ◆ ◆ ■目次 どんな教師になれるかをチェック教師の仕事を辞めたいと思った理由
【現場のリアル】理想と違った教育現場にモヤモヤ…でも「教える」ことは、あきらめなくていい。 「夢だった教師になれたのに、なんか違う…」 そんな違和感を、あなたも感じていませんか? 「子どもたちの未来をつくる仕事がしたい」 「生徒一人ひとりに寄り添いたい」 ――そう思ってこの道を目指したはずなのに、 いざ現場に出ると、理想と現実のギャップが大きすぎる。 たとえば、支援学校に配属されたある教師のエピソード。 校長先生から放たれたのは、なんと―― 「その子の将来?諦めた方がいいよ」…という、信じられない一言。 ……あなたなら、どう感じますか? ▼卒業した学校の先生は「理想」だった。でも、それがすべてじゃなかった。 たしかに、あなたの母校の先生は素晴らしかったかもしれません。 教育に情熱があり、いつも生徒を想ってくれた存在。 でも残念ながら、どの現場もそうとは限らないのです。 「生徒の良さを伸ばす」どころか、「どうせこの子には無理だ」と線引きしてしまうような空気。 理想とする「教師像」とのギャップに、心がすり減っていく…。 ▼「生徒の未来を変えたい」その想いが強いほど、つらくなってしまう人もいる 本気で子どもと向き合いたい。 どんな子でも、その子らしさを活かして伸ばしてあげたい。 ――そんな純粋な気持ちを持つ人ほど、現場のリアルに苦しんでしまうのも現実。 実際に、金輝 発達障害カフェバーのお客さんの中にも、 教育現場でうつ病を発症してしまった元教師がいました。 「思ってた仕事と違った」 「誰のために頑張ってるのか分からなくなった」 そんな理由で退職してしまった人も、決して少なくありません。 👉【関連リンク】うつ病で休職しやすい職業ランキング ▼でも、大丈夫。教師の「舞台」は、学校だけじゃない! ここで知っておいてほしいことがあります。 「教育」は、学校だけのものじゃない。 発達障害があるからといって、教師になれないわけじゃない。 むしろ、発達障害があるからこそ、子どもの気持ちに寄り添えることだってある。 塾・フリースクール・オンライン家庭教師・特別支援教室… いま、あなたが輝ける教育現場は、想像以上に広がっています。 ▼「教師になれるか」じゃなく、「どこで教えるか」が大切 もし今、 「学校では無理かもしれない」 「自分には向いてなかったのかな…」 そう感じているなら―― それは「あなたが悪い」のではなく、「場所」が違っただけかもしれません。 あなたの想いを必要としている現場は、きっとどこかにあります。 「先生」という仕事を諦める前に、 「どんな場所で、どんな子どもと向き合うか」を一緒に見つけていきましょう。 ▼あなたが「教えたい」と思った気持ちは、ウソじゃない。 ・現場のリアルにショックを受けても ・職員室で孤独を感じても ・生徒の将来を本気で信じられるなら あなたは、きっと「教える才能」があります。 学校の枠を超えた場所で、その力を活かせる道もあるんです。 ◆ ◆

——————しっかりと自己分析をすれば教師になれる!
教師の仕事を目指すためにチェックすること
【先生になりたいけど不安…?】発達障害の私が「教える仕事」に気づけたきっかけ 「国語の授業が大好きだったから、国語の先生になりたい!」 「小学生の頃、担任の先生が優しかったから、私もそんな先生になりたい!」 ──そんな風に、「学生時代の憧れ」を胸に、教師を目指す人は少なくありません。 でも、ちょっとだけ立ち止まって考えてほしいんです。 本当に、あなたが目指してるのは「教師の仕事」?それとも「学校という環境」? 実はここが、発達障害のある方が「教師を目指すときの最大の落とし穴」なんです。 ▼教えることが好きでも、「誰に教えるか」で向き不向きが変わる! たとえば── ✔ 子どもが好き → 小学校の先生に向いてる ✔ 思春期の対応が苦手 → 中学校の先生はストレスに? ✔ 集団より1対1が得意 → 保健室の先生や家庭教師が天職かも! 「教壇に立つ教師」だけが「先生」ではありません。 あなたの“伝えたい想い”を、もっと自然に発揮できる場所が、実は他にもたくさんあるんです。 ▼発達障害と教師志望がぶつかるとき、見落としがちな視点とは? 発達障害のある学生ほど、学校という環境に強い思い入れを持っていることがあります。 ・授業中、先生に褒められた記憶 ・学校だけが「安心できた場所」だった ・「あの先生みたいになりたい」という憧れ とても素敵な気持ちですし、それが原動力になることもあります。 でもだからこそ── 「学校以外にも、人を教える仕事がある」という視野を持ってほしいんです。 ▼教えることが得意なら、「カウンセラー」という選択肢もある 実は、発達障害の特性と相性が良いと言われている職業のひとつに「カウンセラー」があります。 ・教室のような集団ではなく、1対1でじっくり向き合える ・相手に合わせたペースで関わることができる ・相手の成長を見守りながら、少しずつ関係性を築いていける 「教える=学校の先生」だけじゃないって、少し希望が湧きませんか? ▼どうしても教師になりたいなら「障害者雇用×公務員」という道も! 「やっぱり私は学校の先生になりたい」 「どうしても、あの場所に立ちたい」 そんな気持ちがあるなら、「障害者雇用」という制度を活用して教師の道を目指すことも可能です。 自治体によっては、障害者枠で教員採用試験を受けられる制度もありますし、養護教諭や支援学級の教員として活躍されている方もいます。 あるいは、教職には就かずとも、学校環境に関わる公務員の仕事という選択肢も。 ▼あなたの「教えたい気持ち」は、いろんな形で花開く ・発達障害があるからって、教師を諦める必要はありません。 ・でも“教える”にもいろんなカタチがあることを知ってほしい。 ・自分の特性に合った場所なら、もっと楽しく・長く続けられます。 「教師になる」だけがゴールじゃない。 あなたの「伝える力」は、あなたが思ってるよりずっと武器になりますよ。
教師になれるけど発達障害にとって向き不向きがはっきりと変われる仕事なのね。
教える生徒が勉強ができるか、男女比、個別か集団かに寄ってもまるで違う💕 しっかりと私に合った授業ができるところを選べばずっと続けれるのね✨ 学校の教師になれる人の特徴
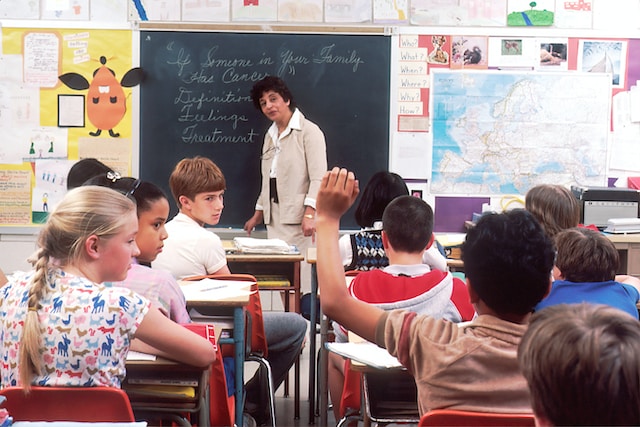
——————学校の先生に憧れて教師を目指す⁉️
学校の先生が向いてる人の特徴
【発達障害でも教師になれる?】授業中に落ち着けないあなたこそ、実は向いてるって話。 「え…また生徒が雑談してる」 「眠ってる子ばっかりで、授業が進まない」 「注意しても聞いてないし、なんか空気が回らない…」 そんな「てんやわんや」な授業風景。 でも、それ…実はあなたの「強み」かもしれません。 ▼ ADHDの教師こそ、型破りな「本物の先生」になれる理由 「ADHDだと教師なんて無理」――そんな声、聞こえてきそうですよね。 でも、実際はその逆。じっとしてられない、静かすぎると落ち着かないタイプこそ、教室では無敵だったりします。 なぜなら、予測不能な“ハプニング”が日常茶飯事の教室では、 「型にはまらない感覚」がむしろ武器になるから。 授業中に生徒が雑談する? → 会話の中からヒントを拾って脱線授業スタート! 理解できない子が多い? → じゃあ今から全員巻き込んだ「体感授業」に切り替え! こういう柔軟な対応って、実はADHD気質の教師にしかできないんです。 ▼ いじめに負けないコツは「味方を生徒にする」こと でも、教師の世界は甘くない…。 実際、「教員間のいじめ」に耐えられず辞めたという声も少なくありません。 そんな中で発達障害を抱えて働くなら、生徒との信頼関係を味方に付けるのが最強の対策です。 というのも、生徒から好かれてる先生をいじめようとすると―― いじめをする教師が「生徒の敵扱い」になってしまうから。 これは意外と、効きます。 ▼ アスペルガー向けの教師/HSPの先生は「優しいフォロー役」として超重要 もしあなたがADHDではなく、アスペルガー傾向やHSPタイプだったとしても心配はいりません。 むしろ、あなたには怖い先生の後ろで光るポジションがあります。 たとえば、怖い先生に怒られた不良生徒が教室の隅で不貞腐れていたら…。 あなたの出番です。静かに、優しく話しかけてあげましょう。 「先生がいるから、学校も悪くないな」 そんな風に思ってもらえたら、もうそれは「かけがえのない教師」の一歩目。 ▼ 発達障害だからこそ教師になれる。むしろ、それが才能。 発達障害の特性は「個性」だけでなく「戦力」でもあります。 授業中に落ち着かない → 動きがあるからこそ楽しい授業になる。 静かな空間が苦手 → 子どもたちの雑談にすぐ気づける。 集団に疲れやすい → 一人ひとりの子を丁寧に見る視点がある。 大切なのは、“教師の型”に自分を当てはめるんじゃなくて―― 「自分に合った教え方」で輝ける場所を選ぶこと。 あなたの特性が、子どもたちの未来を照らす光になるかもしれません。 だから、自分を諦めないでください。
学校の先生だとどちらかといえばADHDよりのお仕事になります。
もし、あなたがHSPアスペルガーならフォローする側に回るようにしましょう。 教員同士のいじめにも巻き込まれないように生徒と仲良くしないといけません。 子供が好きなら放課後デイサービス
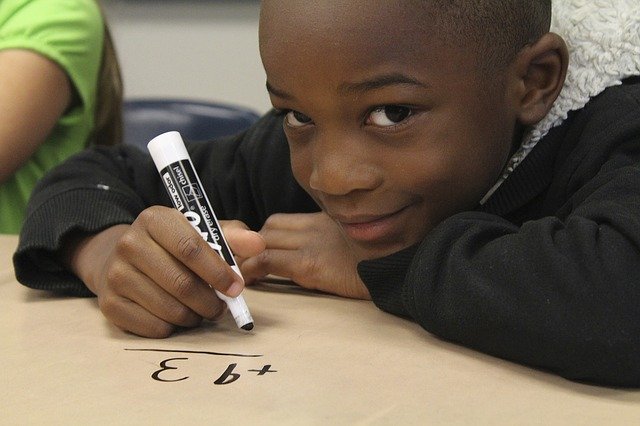
——————放課後デイサービスで発達障害の子供を教える⁉️
放課後デイサービスの先生が向いてる人の特徴
【学校が嫌いだったあなたへ】発達障害の子どもを「のびのび育てる教師」という選択肢 かつてのあなたは、 「できないこと」をできるまで叱られ、 「みんなと同じじゃないとダメ」と押しつけられ、 そのたびに「自分には向いてないのかも…」と感じていませんでしたか? でも――。 その経験こそが、今“必要とされている教育”の現場で活きるんです。 「できない子を叱る教育」に、心から違和感があったあなたへ もしあなたが今、 ・生徒は「できる子」じゃなくてもいい ・のびのびと成長してほしい ・無理に型にハメる教育にうんざりしていた そう思っているのなら、放課後等デイサービスという選択肢があります。 そこでは、発達障害や知的障害を持つ子どもたちが、プレッシャーから解放された場所で“その子らしく”成長しています。 あなたが学生時代に「こんな先生がいてほしかった」と思ったような存在に、今度はあなた自身がなれるんです。 「発達障害の子にもスパルタを」と思ってしまうなら、それは別の道。 たしかに、 「まだ子どもなんだから厳しくしないと」 「発達障害といってもそんなに能力は変わらない」 「中学受験くらい乗り越えてもらいたい」 そんな考えが浮かぶこともあるかもしれません。 でも、もし“厳しさで鍛える教育”を本気でやりたいなら、進学塾の先生や受験指導型の教育現場のほうが、きっと向いています。 発達障害を持つ子に必要なのは、 「早くできるようになること」ではなく、 「安心してできるようになるまで寄り添うこと」だからです。 学校が嫌いだったあなただからこそ、子どもに「好きな時間」を与えられる 「自分が変えたいと思った教育を、現実にしたい」 その想いがあるなら、放課後デイサービスの先生は天職かもしれません。 実際に、 ・学校が苦手だった元・学生 ・発達障害当事者の元・不登校生 ・大人になって発達障害を診断された人 …そんな人たちが今、放課後等デイサービスの現場で活躍しています。 特別な資格がなくても、未経験からスタートできる職場もあります。 必要なのは「子どもにとって味方でいたい」という気持ちだけ。 発達障害の子どもに必要なのは、理解者であり応援者。 教師って、なにも黒板の前に立つ人だけじゃない。 あなたが昔ほしかった「味方の先生」に、今こそなりませんか?
発達障害で学生時代に苦しんでいた過去がある。
それなら、学校の先生よりも放課後デイサービスが向いてるかもしれません。 特に発達障害を持ってる子供にのびのびとした教育をさせたいのであればおすすめの仕事となります! 塾や家庭教師のバイト 人を支えたい気持ちがあるなら就労移行支援

——————同じ年の人を社会に出るために教えたいなら就労移行支援⁉️
就労移行支援が向いてる人の特徴
【仕事に失敗しても教師になれる!?】挫折を強みに変える「第2の教壇」の見つけ方 「もう一度、人に“何か”を教える仕事がしたい」 でも―― ✔ 就職に何度も失敗して自信がない ✔ 人間関係が怖くなって引きこもった ✔ 発達障害の特性で働くのがつらい… そんなあなたへ。 学校じゃない場所で、教師のように人を支える仕事があることをご存じですか? その名も【就労移行支援のスタッフ】というお仕事です。 ■「学校の先生じゃない教師」という選択 就労移行支援とは、発達障害や精神障害などのある人が「就職に向けた準備」をするための福祉サービス。 利用者の多くは、かつてのあなたと同じように―― 「働きたいけど怖い」「向いてる仕事が分からない」 そんな不安を抱えてきた人たちです。 だからこそ、挫折を経験したあなたの言葉に救われる人がいる。 「失敗した自分が教えるなんて…」と思っていた人ほど、現場で頼りにされていたりします。 実際に元・学校教師からの転職例も多数! 教えるスキルを「福祉の現場」に生かすことができるんです。 ■発達障害があっても大丈夫?──その答えはYES。 「自分自身も発達障害があるのに、誰かをサポートできるの?」 そんな声も聞こえてきそうですが、むしろ強みになります。 なぜなら就労移行支援には利用期限が2年と決まっていて、長すぎる人間関係に苦手意識がある人でも安心して関われます。 「誰かの困りごとに、自分の体験を重ねて寄り添える」――これこそ、支援の現場で最も重視される“資質”なのです。 ■もっと長く寄り添いたいなら「就労継続支援」という道も 「2年じゃ足りない、もっと長くサポートしたい」 そんなあなたに知ってほしいのが、就労継続支援(A型・B型)というもう一つの選択肢。 でも不安だと思うなら、就労継続支援B型で働く職員の悩みのページも読んで知的が重い人でも対応できるかも合わせて読むとより理解が深まります。 A型:簡単な仕事をしながら、給与も発生する働く場所 B型:よりサポートが必要な方に、生活リズムからサポートする環境 知的障害がある方を、もっと長期的に、じっくり教えていきたいなら、この分野も視野に入れておくと良いでしょう。 👉 「A型・B型の違いって何?」という人は、A型作業所とB型作業所の違いページも合わせてチェック! ■教師という「肩書」にこだわらない、教える人生がある。 黒板がなくても、教室がなくても。 あなたの経験を必要としている「学びの場」は、まだまだたくさんあります。 「教師になりたい」じゃなくて、「誰かの力になりたい」 その気持ちさえあれば、福祉という教壇であなたはもう立派な先生になれるんです。 不良を教えたくないのであれば塾

——————塾ならそれなりに頑張れる生徒だけ教えることができる⁉️
塾の教師が向いてる人の特徴
「発達障害の私でも教師になれる?」…その答えは、“学校”じゃない場所にあった。 黒板の前に立つたび、不安になる。 真面目な子にはちゃんと教えられるのに、 不良が騒ぎ出すと、もう何も言えなくなる—— 「授業崩壊」 「いじめっ子の反抗」 「教室が怖い」 そんな現実に、心が折れそうになったあなたへ。 実は、「学校の教師」じゃなくても 【教える才能】を活かせる場所があるんです。 ▼それが、「塾の先生」という選択肢。 塾なら、いじめの対応も、生活指導も、「できなくて当然」なんです。 「宿題を忘れる生徒?それくらいなら全然OK。」 「授業中に寝てても?学校ほど気にしなくて大丈夫。」 「いじめ?塾なら、そんな子は来ない。」 そう、塾という場所は、教えることに集中できる場所なんです。 ▼発達障害のある人ほど、塾の先生に向いている理由 ✅ 教えたい教科だけに集中できる ✅ 学校よりも静かで環境が整っている ✅ 教室崩壊などの心配が少ない ✅ 生活指導など「苦手な仕事」を任されない ✅ 成績別クラスで教えやすい雰囲気がある 実際、大手塾では発達障害の特性を理解している職場も増えており、 得意分野に特化して活躍する先生が増えています。 ▼「でも、教師を諦めたほうがいいのかな…?」と思っているあなたへ 安心してください。 「学校の先生がすべて」じゃありません。 むしろ、発達障害の人が無理して クラスの空気を読もうとして、 反抗的な生徒を相手に毎日ストレスを抱えるよりも—— 「この教科が好きだから教えたい」 「真面目な子に、ちゃんと届く授業をしたい」 そんな思いを大切にできるのが、塾なんです。 教師になる夢、あきらめなくていい。 「発達障害があるから…」と教師をあきらめるのではなく、 「教え方を変える」ことで夢を叶えることはできます。 生徒を選べる。 教科を選べる。 余計な業務はしなくていい。 あなたの特性を「武器」に変えられる働き方が、 塾講師という道にはあります。 大勢の人を見れないなら個別指導

——————個人教室の生徒を集めるコツは継続だけ⁉️
個人教室の開業が向いてる人の特徴
「発達障害だからこそ、あなただけの教室が開ける」 ~「型破り」でも「心に響く先生」になる方法~ 「授業のやり方にこだわりがある」 「決められた教科書通りなんてつまらない」 「自分なりの工夫で、生徒を笑顔にしたい」 そんな「情熱」と「オリジナリティ」を持つあなたへ──。 実は今、「発達障害 × 教師」という働き方に、新しい選択肢がどんどん広がっています。 たとえば、こんな道があるんです。 ■ ピアノ、習字、英語──「好き」を仕事に! 昔ながらの【個人教室】こそ、自由度バツグン! あなたのペースで、あなたのスタイルで、生徒に向き合えます。 授業に正解はありません。だからこそ、個性が最大の武器になるんです。 ■ オンライン講師という選択肢も! 場所がない? そんなときは【オンライン教室】。 今人気のオンライン講師ならリトルスパーク 発達障害があっても、自宅にいながら「あなただけの教室」が開けます。 ■ 個別塾や家庭教師なら、生徒と一対一 「集団が苦手…」という方には【個別レッスン】がおすすめ! 大人数に気を使うことなく、生徒ひとりひとりとじっくり向き合えます。 しかも、授業に創意工夫を加えやすいのがポイント◎ ■ 教えるのが得意=カウンセラーにもなれる 「話を聞くのが得意」「共感力がある」なら、 カウンセラーという道もアリ。 「教える」ことと「寄り添う」ことを両立できる、まさに発達障害特性を活かせる仕事です。 発達障害だからこそ、「自分らしい先生」になれる! 学校の先生だけが「教師」じゃありません。 むしろ、決まりきった授業が苦手だからこそ、自由なスタイルが似合うんです。 あなたにしかできない教え方で、生徒の心をつかんでみませんか? 「発達障害でも教師になれる?」 その答えは──もちろんYES。 しかも、「あなたらしさ」を最大限に活かせる形で、です。 ▶ 自分だけの教え方で生徒を笑顔にしたい方はオンライン講師ならリトルスパーク まとめ
📚【発達障害でも教師になれる?】 〜苦手を避けて“あなた流”で教えるという選択〜 「発達障害だから、教師は無理かもしれない」 そんな風に、あきらめていませんか? でも実は―― 発達障害の特性を活かして、「教えるプロ」として活躍している人たちがいるんです! 教師という仕事は、向き不向きがハッキリ出る職業。 だからこそ大事なのは、あなたが“教えやすい”環境を選ぶこと。 例えば—— ・専門教科だけを集中して教えるスタイル ・騒がしい子どもたちとの距離感がちょうどいい支援学級 ・マニュアル通りじゃない柔軟な指導が許される学習塾 など、発達障害の方が力を発揮できる現場は思っている以上にたくさんあるんです! 事実、「普通の教え方」では上手くいかなかった人が、 教え方をちょっと変えただけで“教える楽しさ”を見つけたケースも多数! さらに、 「発達障害だからこそ、生徒の気持ちに寄り添える」 「空気が読めない=余計な気を使わず本音で指導できる」 そんな強みを活かして、信頼される先生になる人も増えてきています。 あなたに必要なのは、苦手を責めない教え方を選ぶ勇気。 無理に型にはまらなくてもいいんです。 あなたにしかできない教え方で、教育の世界を変える教師になる。 さあ、あなたの教える力を活かせる場所—— 探してみませんか?
それでも教師の仕事が難しいと思うのであれば障害者雇用で働くことを目指しましょう。
障害者の就・転職ならアットジーピー【atGP】 できる教師の仕事を相談すればやりたい教師の仕事を目指すことができます。 が良いです。 未経験でも教師になれることができます! どれが良いか判断ができないのなら無料なので2つとも登録して後から決めましょう。 |