金輝 発達障害アートカフェ・バー
生活できない就労継続支援B型の職員を辞めたいなら
生活できない就労継続支援B型を辞めたいと思ったら
生活できない…就労継続支援B型の職員を辞めたいあなたへ。 「正直、生活が成り立たないんです」 ——そんな声が、今、全国の就労継続支援B型の現場から聞こえてきています。 利用者さんと過ごす時間は楽しい。 笑顔や何気ない会話が、日々の原動力になっている。 だけどその裏側には、厳しい現実があります。 国からの報酬単価は毎年のように削られ、上がることはほとんどない。 職員の給料は据え置き、いや、むしろ年々厳しくなる一方です。 事務作業に追われる日々。 申請書類、モニタリング、アセスメント… 本当はもっと、利用者さんと関わりたいのに。 ——でも、このままで本当にいいの? ——この仕事を続けて、将来はどうなるの? そんな葛藤を抱えながら働く職員は、決してあなただけではありません。 中には「もう限界だ」と辞めていった人もいます。 ただ、転職先でまた同じような悩みにぶつかり、後悔してしまった人も少なくありません。 「辞めたいけれど、この仕事にやりがいはある」 「でも、生活は限界」 「他の仕事でも、自分はまた同じことを繰り返しそう」 ——そんなジレンマを抱えているあなたに、今この記事を届けたいのです。 この記事では、「就労継続支援B型の職員を辞めたい」と悩むあなたが、 ・何に苦しんでいるのか ・辞めるとどうなるのか ・後悔しない選択をするために何を考えるべきか …そのヒントをお伝えします。 辞めるのは悪いことではありません。 でも、「次」を見つけるには、今の悩みをきちんと整理する必要があるのです。 将来が不安で、ストレスが限界に近づいているあなたへ。 少しだけ、立ち止まって読み進めてみてください。 職員の悩み ◆ ◆ ■目次 就労継続支援B型の職員を辞めたいと思った理由
就労継続支援B型の職員を実際に辞めた人の理由
「辞めたい」と思うのは、あなたが真剣に向き合っている証拠です。 ——就労継続支援B型の職員として働く中で、ふとよぎる「辞めたい」の気持ち。 それは、あなたがちゃんと利用者と向き合っているからこそ、生まれている感情かもしれません。 「もっと、この人には可能性がある」 「就職して、自立して、社会で羽ばたいてほしい」 そう願って支援をしてきたのに、現実は簡単じゃない。 知的障害がある利用者さんの中には、一般就労ではなく、支援のある環境でこそ力を発揮できる人もいます。 ——それでも頑張る姿。 支援を受けながら、就労継続支援B型でコツコツ働くその日々。 実はそれだけでも、十分に「自立」しているのかもしれません。 でも、職員の側が「成長させなきゃ」「就職させなきゃ」と焦ってしまうと、無意識に厳しく接してしまうこともあります。 「この人はここがダメだ」——そんな思いを少しでも抱くと、利用者さんには伝わってしまいます。 知的障害がある人たちには、言葉にならない「空気」を感じ取る力があります。 だからこそ、見下されていると感じると、関係が一気に崩れてしまうこともあるのです。 それでも、制度はどんどん厳しくなるばかり。 国からの補助金は減る一方。 申請方法も毎年変わって、事務作業も増えるばかり。 ——本当は、もっと1人ひとりとじっくり向き合いたいのに。 現実は、大勢を同時に見なければいけない。 1対1の支援が得意だったのに、それができず、苦しんでいる職員も少なくありません。 さらに深刻なのは、上司や経営者が「利用者の人生」より「利益」を優先している場合。 現場の声を無視して、支援の質よりも助成金重視の運営をしている——そんなB型事業所も、実際に存在しています。 ※このあたりの闇が気になる方は、助成金目当ての怖いA型事業所はやめとけの記事もぜひご覧ください。 ——「辞めたい」と思うのは、あなただけじゃない。 むしろ、真面目に向き合っている人ほど、苦しくなる仕組みになっているのが、今の就労継続支援B型の現実です。 この先どうすればいいのか? 辞めることは逃げなのか? それとも、新しい一歩なのか? この記事では、あなたが後悔のない選択をできるよう、さまざまな視点から「就労継続支援B型を辞めたい職員の本音」に迫っていきます。 もし、市区役所や各地域の議員さんに法改正の依頼をするのであれば 最低賃金の減額の特例許可申請の有無の評価もスコアに取り入れていただきたい 監督機関への提出又は申請書類、不正(間違った)内容の申請を行なった場合の罰則の明確化をしていただきたい スコア表はその施設を評価できる資料なので、一括して公表するサイトの作成をするか法で強制していただきたい。 そもそもスコア表をホームページ上に公表していないところも見受けられるののが問題だ 利用者の雇用を守り、安心して職業経験を積んでもらうためにも、特にA型では、その事業所で行なっている事業の事業性評価(事業として成立するのか、商売として成立するのか)の確認も行うべきだ を伝えるようにしましょう 就労継続支援B型—— この現場に立つ職員たちが、心のどこかで「辞めたい」と感じる理由のひとつ。 それが、果てしない事務作業の多さです。 国の制度が変わるたびに、申請の手続きはどんどん複雑に、厳しく。 年を追うごとに増していくその負担に、現場の職員たちは静かに、でも確かに疲弊していっています。 「本当に支援が必要なのは誰なのか?」 「どうすれば、もっと楽に、もっと現場の声が届くようになるのか?」 実は、この理由で辞めたいと悩んでいる職員の多くは、利用者を第一に想い、支援に真剣に向き合っている方ばかり。 だからこそ、事務仕事とのギャップに心を削られてしまうのです。 逆に、補助金の申請がうまい、いわば「お金儲け主義」の事業所ほど、こうした事務作業をスムーズにこなす仕組みを持っていたりします。 皮肉なことに、本当に真面目にやっている人たちのほうが報われにくい構造——それが、今の制度のひとつの歪みかもしれません。 それでも、事務作業のスキルを少しでも磨きたいと願うなら、ユーキャン ——それでも、本質的な課題は残ったまま。 本当に利用者を想う支援者が、安心して働き続けられる仕組みは、いつになったら整うのか。 個人的な私の意見としても、この現状を見過ごすことはできません。 もし、少しでも現場が楽になるような方法があるのなら—— それを国が真剣に受け取り、制度に反映してくれる日が来ることを、心から願っています。
就労継続支援B型は、仕事ができない利用者のために訓練を受ける施設です!
利用者に対して仕事ができるようになってもらいたい気持ちが強いと空回りしてしまいます。 先ずは、作業ができるまで待ってあげることを意識していくことが大切です。 ◆ ◆ 就労継続支援B型の職員がおすすめなできない人の特徴
「就労継続支援B型の職員を辞めたい」と感じたあなたへ——その理由、実は「向いていないサイン」かもしれません。 「このままじゃ、ダメかもしれない」 「利用者の就職を本気で応援したい。でも現場はそうじゃない…」 そんな気持ちで苦しくなっていませんか? 就労継続支援B型は、一般就労が難しい知的障害のある方が、支援を受けながら働ける場所です。 中には、社会復帰に成功した利用者もいますが、どれだけ工夫しても、それが難しい方もたくさんいます。 もしあなたが—— ・一般就労への定着に強いこだわりを持っている ・社会人スキルを身につけさせたい気持ちが強すぎる ・「成長させなきゃ」といつも焦っている …そんなタイプであれば、もしかすると就労継続支援B型の職場は向いていない可能性があります。 もっと、人の成長に深く関わりたいなら—— 「教師」という選択肢もあります。 教育現場なら、難しい内容を教えることも、達成感を得ることも可能です。 気になる方は、あなたがどんな教師になれるかチェックする方法もぜひ活用してみてください。 就労継続支援B型で大切なのは、「ゆっくり見守ること」 焦らせたり、無理にやる気を引き出そうとしすぎてはいけません。 簡単な作業でも、時間がかかっても、利用者のペースを尊重して寄り添う。 それがこの現場で求められる支援スタイルなのです。 そして、給料が低くて「このままでいいのか」と不安になる方も多いでしょう。 ですが、利用者の多くは精神障害者保健福祉手帳1級または2級を取得しており、障害年金の支給対象となります。 そのため、経済的に困っているのはむしろ職員の方——というのが現実かもしれません。 「もう辞めたい」と思うあなたへ。 それは、モチベーションが落ちているサイン。 無理を続けて心身を壊す前に、一度立ち止まって「別の福祉の道」を考えることも、大切な選択肢です。 もし、福祉や介護の仕事にやりがいを感じているなら、次の職場で新しいスタートを切りませんか? 以下の転職支援サービスがあなたの再出発を応援してくれます。 【おすすめの転職サイト】 ■ 介護・福祉の転職サイト『介護JJ』 あなたに合った福祉職を、専門アドバイザーがサポート。 職場環境・給料・残業時間など、リアルな情報も分かるから安心! ■未経験でも安心な 医療・介護・福祉の求人探しは【ジョブソエル】 医療・介護・福祉業界が初めてでも大丈夫。 研修制度が整った職場を紹介してくれるから、50代からの再就職にも強い! 就労継続支援B型の現場で「辞めたい」と思ったのは、あなたが真剣に仕事に向き合ってきた証拠です。 今までの経験を活かしながら、もっと自分らしく働ける場所を見つけていきましょう。
すぐに就職させたいと思って利用者と接したら嫌われてしまった💢
だけど、利用者の人生を考えるともっと頑張って欲しいのが正直なところ💦 仕事の訓練をもっと頑張らないと今後の人生の生活ができないと考えると辛い………。 意味ないと思われる理由 利用者のやる気がなく愛着が湧かないなら利用者のやる気を出す方法
就労継続支援B型の現場には、知的障害を持つ方が多く在籍しています。 だからこそ、簡単な作業でさえ難しく、うまくできないことがある—— そんな利用者の姿に、職員の中には苛立ちを覚えてしまう人もいます。 「なぜこんなこともできないんだろう」と。 「教えても意味がない」と感じてしまう瞬間もあるかもしれません。 しかし、そこで怒りをぶつけてしまったら—— 支援ではなく、ただの押しつけになってしまう。 ひどい事業所では、こうした苛立ちがエスカレートし、 パワハラまがいの対応や言葉の暴力へと発展してしまうケースさえあるのです。 もしあなたが、そんな現場で立ち止まってしまっているなら。 それは「あなたが悪い」のではなく、「支援のあり方に疑問を感じた」からこそ。 だからこそ、市役所に相談してみてください。 あなたの勇気が、利用者を守る大きな一歩になります。 就労継続支援B型で大切なのは、「教える」のではなく「寄り添う」こと。 友達のような感覚で、無理に変えようとせず、そばにいる姿勢。 それが何よりも、利用者の心に届く支援です。 知的障害がある利用者の中には、職員の心を鋭く見抜く人もいます。 「バカにされている」と感じれば、たちまち信頼関係は崩れてしまう。 だからこそ、支援者自身も自分のメンタルを整えることが必要です。 もし、自分の心の整え方を学びたいなら—— ヒューマンの通信講座*たのまな『メンタルケア心理士』 支援者としての軸を強くしていくこともできます。 けれども現実には、やる気のない利用者も確かに存在します。 障害によって、「働く必要がある」という認識そのものが難しい人もいます。 中には、経済的に裕福で、働かなくても生活が成り立つ環境にある方もいます。 そんな姿を見て、「頑張る意味」を見失ってしまう職員もいるのです。 利用者が支援によって「守られすぎる」一方で、 支援する職員は、補助金の減額や低賃金に苦しんでいます。 職員のほうが「生活できない」と悩む、逆転した現実があるのです。 さらに悪質なケースでは、不正に補助金を受け取る業者が生き残り、 真面目に支援をしている福祉事業所ほど潰れていく—— そんな矛盾すら存在しています。 だからこそ、願わずにはいられません。 就労継続支援B型の現場が、もっと「人にやさしい場所」になっていくことを。 支援する人が報われ、支援を受ける人も安心できる、そんな福祉の形を。 国の力で、制度が少しずつでも良くなっていく未来を—— 現場の一人ひとりが、本当にそう願っています。 マルチタスクが苦手過ぎて大勢の面倒が見れないなら
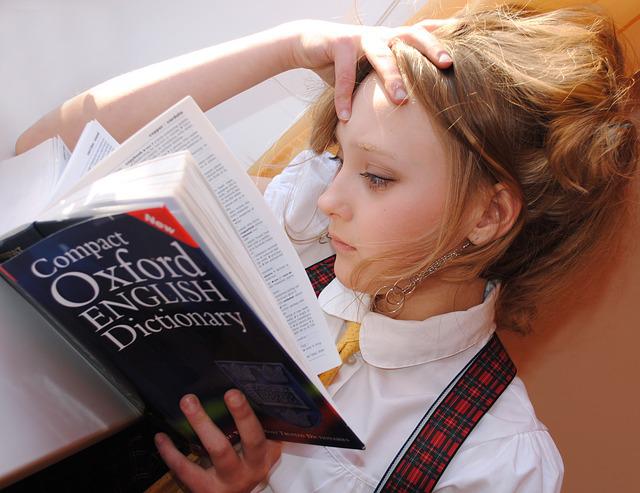
——————大勢の利用者を見るよりも一人に限定した支援
大勢の利用者の面倒が見れないなら
「就労継続支援B型の職員を辞めたい」——そう感じてしまう理由の一つに、発達障害の特性と業務のギャップがあります。 特に、発達障害の傾向がある職員にとっては、「マルチタスク」が大きな壁。 目の前の作業や利用者に集中しすぎてしまい、他の利用者の様子に気づけない—— そんな場面に心当たりがある方もいるのではないでしょうか。 「今日は一日、この人の支援に集中していたな…」 そう思って振り返ると、何人かの利用者がほとんど作業していなかったことに気づく。 1日の終わりに、他の職員や上司から指摘されて落ち込んでしまう。 そして気づけば、「もう、辞めたい…」と感じてしまう。 実はそれ、あなたの能力不足ではありません。 「全体を見渡すことが苦手」という特性に、業務の構造が合っていないだけなんです。 でも、少しの工夫で改善できることもあります。 たとえば、サボらない利用者を信頼し、その人たちにはあえて目を配らないようにする。 して、トラブルが起きやすい人や気になる人ほど、なるべく近くの席に配置する。 これだけで、意識の配り方にメリハリがついて、負担が軽減されることもあります。 それでも、「やっぱり自分にはこの環境が合わない」と思うなら—— 無理に続ける必要はありません。 あなたに合っているのは、もしかすると「ホームヘルパー」のような1対1の支援かもしれません。 ホームヘルパーなら、目の前の一人にじっくりと向き合うことができます。 マルチタスクではなく、シングルタスクに集中することが求められる支援のかたち。 その方が、本来の力を発揮できて、利用者にも喜ばれる支援ができるかもしれません。 支援職には、あなたの特性が活かせる場所がきっとあります。 医療・介護・福祉の求人探しは【ジョブソエル】 無理して「できない自分」を責めるのではなく、 「向いている環境」を選び直すことも、立派なキャリアの一歩です。 就労継続支援B型の職員として苦しんでいるなら、 まずは「自分に合った支援スタイルとは何か?」を見つめ直してみてください。 それが、あなたらしく働ける未来への第一歩になります。
やる気のある利用者まで、ずっと監視しなくてもオッケーなのです。
ほっとくと、サボりだす人だけをしっかりと見るぐらいでも構いません。 ただし、完全一人の支援をしたいのであればホームヘルパーの仕事も良いかもしれません! 営業ができず利用者に仕事を与えることができないなら

——————利用者に仕事の訓練ができる
就労継続支援B型の利用者ができる仕事
「就労継続支援B型の職員を辞めたい」——そんな気持ちが湧いてくる背景には、仕事の限界が見えてしまうことがあります。 就労継続支援B型に通う利用者さんの多くは、知的障害や発達障害などの特性を持っています。 そのため、できる作業はどうしても限られてしまい、内容も単純作業中心になりがちです。 もちろん、それでも「作業を通じて社会とつながる」ことがB型の大切な目的ではあります。 でも、現場の職員としては—— 「もう少しやりがいのある仕事を用意してあげたい」 「このままで本当に意味があるのか?」 そんな葛藤を抱えることも少なくありません。 例えば、「おしぼりをたたむ仕事」は一見シンプルで取り組みやすそうですが、 単価が極端に低く、作業量に見合わないことも多いのが現実。 職員として「本当にこれでいいのか」と悩みながら日々支援を続けている方も多いはずです。 そもそも、B型事業所において営業力が弱いと、仕事の幅自体が広がらないという問題もあります。 本当は、もっと単価が良くて、利用者にとっても意味のある作業を提供したい。 でも、地域の企業や取引先への営業が得意な職員が少ない、または営業できる体制が整っていない。 そのため、「これしかできない」「この仕事しかない」と、選択肢の少なさに支援者としての限界を感じてしまうのです。 この「物足りなさ」や「ジレンマ」が積み重なって、「もう辞めたい…」という気持ちが強くなっていくのも無理はありません。 そんなときは、無理に理想を追い求めすぎず、できる範囲で工夫していくことも大切です。 どうしても営業が難しいなら、ネット上で仕事を受注できるサービスを活用する方法もあります。 最近では、障害福祉施設向けに業務委託や軽作業を提供してくれるサイトも増えてきています。 もしかすると、今あなたが抱えている「支援の限界」は、「職員個人の努力」でどうにもできない「仕組み」に原因があるのかもしれません。 だからこそ、自分を責めすぎないでください。 そして、今の職場でできることに限界を感じたなら、「よりやりがいのある支援」ができる職場へ転職することも、前向きな選択です。 就労継続支援B型の支援現場には、まだまだ改善すべき課題が山積しています。 でも、あなたのように「もっと良くしたい」と本気で思える職員の存在が、きっと未来を変えていく力になります。 仕事の取り方 利用者を頑張って変えようとして嫌われてしまうなら変わろうとしても変われない理由
「就労継続支援B型の職員を辞めたい」——その気持ちの裏側には、支援の難しさと切なさがあります。 知的障害のある方の多くは、過去に「できないことを無理やりやらされた経験」を持っています。 それは時に、支援とは名ばかりの押しつけであり、本人の心に深い傷を残してしまうことも…。 ある支援学校では、校長先生が担任に対し「生徒の未来なんて考えるな」と語っていた—— そんな現場を目の当たりにして、支援者としての希望を失いかけた経験がある方もいるのではないでしょうか。 本来なら、学校という場所でこそ一人ひとりに合った支援が届けられるべきなのに。 その理想とかけ離れた現実に、胸を締めつけられた職員も多いはずです。 中には、学校の先生から言われた厳しい一言が、何年経ってもトラウマになってしまっている利用者もいます。 ちょっとした指導が、その人の心に一生残る「呪い」のような言葉になることもあるのです。 そして、そうした過去の経験から、B型事業所に来ても 「職員にまた裏切られるんじゃないか」「信用しちゃいけない」 と、構えてしまっている利用者も少なくありません。 そんななかで、「なんとか変わってもらいたい」と思って熱心に指導しようとすればするほど… その想いが「パワハラ」と受け取られてしまうこともあります。 あなたの支援が本気だからこそ、うまく伝わらない現実に苦しみ、「もう辞めたい」と感じるのも、自然な流れかもしれません。 もしあなたが「教えて変えていくこと」に強い関心があるのであれば、よりスキルアップを重視する就労継続支援A型や、 職業訓練に近い支援を行う就労移行支援への転職を考えるのもひとつの道です。 就労継続支援A型で働くことに興味が出たら念のため、同じような悩みが起きないためにも 就労継続支援A型の職員の悩みと辞めたい理由のページをチェックしましょう。 また、「しっかり話を聞く力」を生かしたカウンセラーの仕事もおすすめです。 傾聴型でもいいし、アドバイスを軸としたスタイルでも構いません。 あなたの想いを「正しい場所」で活かせば、支援者としての喜びをもう一度実感できるかもしれません。 事務作業が苦手で耐えられないなら

——————予想以上に事務作業が多い
就労継続支援B型の事務作業がややこしい理由
「支援をしたい」その純粋な想いが、あなたを苦しめていませんか? 就労継続支援B型で働く職員の中には、本当に支援がしたくて飛び込んだ人ほど、 「もう辞めたい…」という気持ちを抱えているケースが少なくありません。 むしろ、現場にいてくれたら嬉しいと思える「理想の職員」に限って、辞めたいと感じてしまう—— そんな現実があるのです。 利用者のことを一番に考え、丁寧に寄り添いながら接する。 だけど、そんな職員ほど「事務作業がどうしても苦手」という壁にぶつかります。 実際、就労継続支援B型の現場では年々国からの申請が厳しくなり、もらえる補助金の額は下がる一方。 物価は上がっているのに、運営はどんどん苦しくなる。 そんな中、事務作業が得意な人ほど補助金の仕組みに強く、 逆に利用者に真剣に向き合っている人ほど、書類業務で悩み、疲れて、辞めたい気持ちを強めてしまうのです。 でも—— ここで踏ん張りたい、乗り越えたいと思うあなたには、方法があります。 まずは、MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)などの資格取得を目指すのも一つの手段。 WordやExcelをスムーズに扱えるようになれば、 苦手だった事務作業も“できること”に変わり、自信を取り戻すきっかけになります。 最初は、パソコン操作に慣れるところからで大丈夫。 「支援したい気持ち」を無駄にしないためにも、スキルアップの一歩を踏み出してみませんか? あなたのその優しさや情熱が、きっと現場の未来を変えていきます。 そして、「辞めたい」から「もっと頑張りたい」へ—— その想いが切り替わる日も、決して遠くないはずです。
実際に、就労継続支援B型で働いてる職員の口コミを聞くと事務作業を苦戦してる方は多いです。
事務作業が致命的にできなさ過ぎて就労継続支援B型を辞めたいと思ってる職員は多いようです。 もし克服したいなら、ユーキャン まとめ
それでも、もし今の職場で続けられるのであれば—— 焦って辞めてしまう前に、今の環境で「次のステップにつながる経験」を積むという選択肢もあります。 就労継続支援B型で働いた時間は、決して無駄にはなりません。 福祉の現場で得た経験は、どんな転職面接でも語れる「強み」になります。 どうせ働くなら、その日々をただ消費するのではなく、学びに変えていく。 それが、自分の未来を少しずつ開いていく道になります。 とはいえ、無理に続ける必要もありません。 合わない仕事を無理して続けるより、向いている仕事を見つけた方が、ずっと輝ける。 そう思いませんか? たとえ就労継続支援B型の仕事をこのまま続けても生活が厳しいと感じたとしても—— それもまた、あなたにとって、かけがえのない「人生の経験」です。 転職を何度か繰り返してしまうことがあっても、最後にたどり着けるのが「自分に合った仕事」なら、それでいい。 失敗や迷いも、あなたの“仕事人生”の一部として、未来の選択肢を豊かにしてくれるはずです。 辞めることも、続けることも、どちらも間違いじゃありません。 大切なのは、あなたの人生を前に進める選択ができるかどうかです。 今の経験を糧に、次の一歩を踏み出していきましょう。
就労継続支援B型の職員側だと、事務作業の仕事が予想以上に多いことがあります。
申請書の書き方など、毎年のようにややかしくなるので苦戦してしまい辞めたい職員は多いのです。 事務作業が苦手なことを克服したいなら、ユーキャン
がおすすめです🎶
もし、もっとリアルな就労継続支援B型の仕事について聞きたいのでしたら金輝 発達障害カフェバーへ是非どうぞ。
「就労継続支援B型」で働いてた過去のある人との交流ができるので先輩達のリアルな意見も聞けます。 |